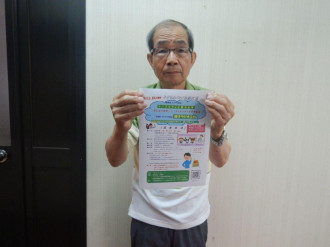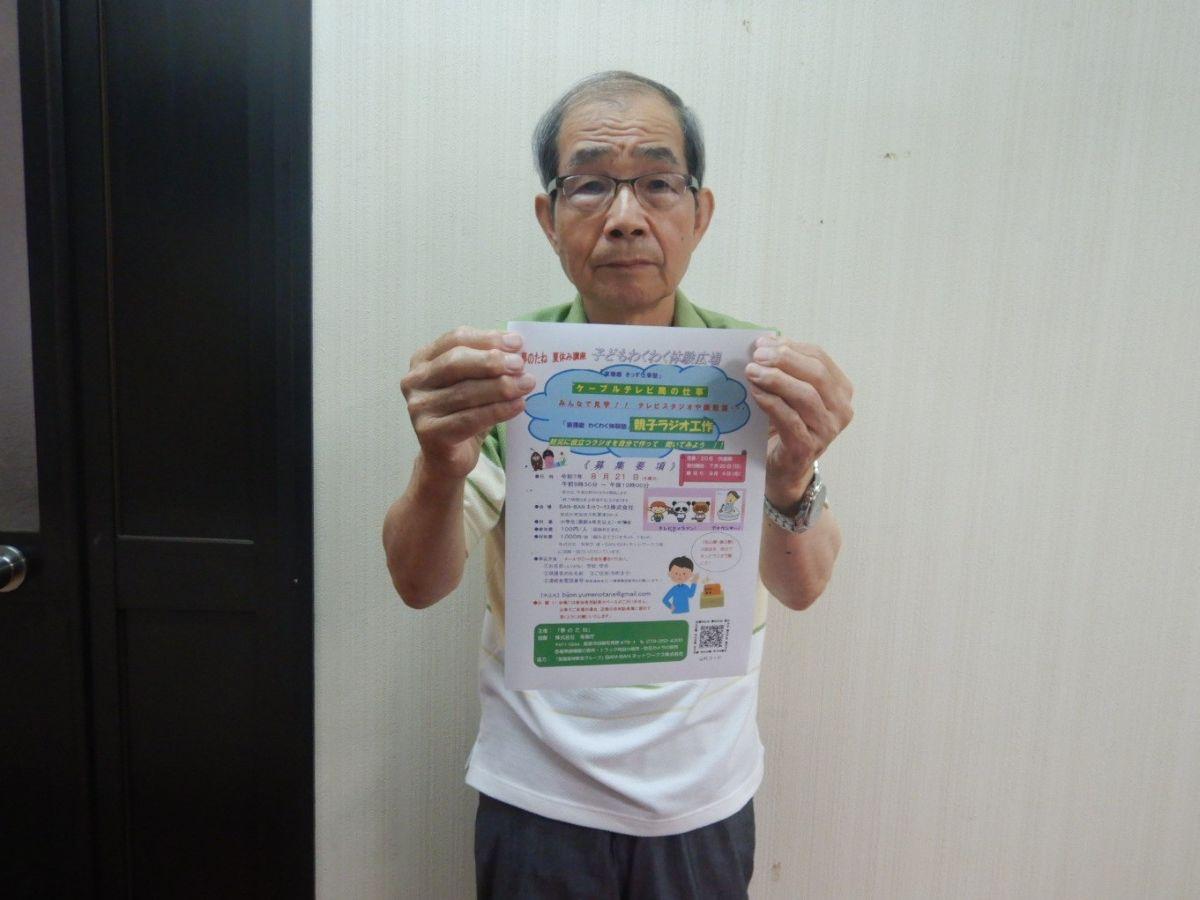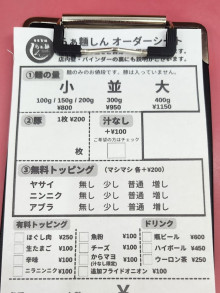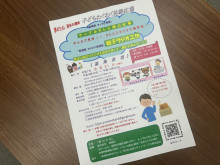日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」(運営:株式会社Clear/東京都渋谷区 代表取締役CEO:生駒龍史)は、兵庫県と神戸市の震災30年事業に共感し、この30年を未来に繋いでいくための企画を年間を通して実施しています。その活動の一貫として、神戸松蔭大学、および神戸学院大学とともに、産官学が連携しての共同研究「灘の蔵・30年熟成酒の想いを未来に繋ぐプロジェクト」を4月から開始しており、中間発表会を7月18日に兵庫国際交流会館で行いました。学生によるお酒の官能評価や、震災当時についてのプレインタビューの様子などが発表され、翌年1月の最終発表会に向けた取り組みへの意欲を新たにしました。
共同研究「灘の蔵・30年熟成酒の想いを未来に繋ぐプロジェクト」中間発表会を開催
世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをブランドパーパスに掲げる日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」は、阪神・淡路大震災にゆかりの深い『現外(げんがい)』という30年熟成 ヴィンテージ日本酒をラインナップしています。
『現外』の醸造パートナーである沢の鶴が蔵を構える神戸市は、「神戸の魅力は人である」という想いを集約したシビックプライド・メッセージ「BE KOBE」に「震災30年を未来につなぐ-持続可能なグローバル貢献都市へ-」を附記したメッセージを発表しています。
神戸の「人の意志」によって生み出された『現外』を有するSAKE HUNDREDもこの想いに共感し、辛い状況から人々の強い意志と希望により発展していった震災からの30年を活かし、未来に繋いでいく企画を、年間を通して実施しています。

この活動の一貫として今回SAKE HUNDREDは、大学コンソーシアムひょうご神戸(※1)の「企業課題解決プログラム」を活用し、神戸松蔭大学(※2)および神戸学院大学(※3)とともに共同研究を4月から開始しています。「現外が持つストーリーを未来につなぎ、寄り添う伝え方とは」という課題に両大学の学生35人が取り組み、沢の鶴などの灘五郷の酒蔵の訪問や、日本酒の市場動向の調査、震災当時についてのインタビューを行うなどして活動を進めてきました。その中間発表会を、7月18日に兵庫国際交流会館で行いました。中間発表会では、神戸松蔭大学と神戸学院大学それぞれの学生が、これまでの活動の報告と学生自身の学び、今後の取り組み予定を発表しました。
※1 大学コンソーシアムひょうご神戸 https://consortium-hyogo.jp/
兵庫県下大学学長会議に端を発する、2006年に設立された団体です。「県下すべての大学による、すべての大学のためのプラットフォーム」として、大学間連携・産官学連携で多様な学びをともに創造し、「若者が育ち、活躍する兵庫」というメッセージを発信しています。
※2 神戸松蔭大学 https://www.shoin.ac.jp/
※3 神戸学院大学 https://www.kobegakuin.ac.jp/
共同研究プロジェクト「灘の蔵・30年熟成酒の想いを未来に繋ぐプロジェクト」
共同研究1)神戸松蔭大学・川口ゼミプロジェクト震災経験の風化を危機に感じ、学生目線で震災を考え神戸の未来をつくり上げることを狙う
神戸松蔭大学は、阪神・淡路大震災で被害が甚大だった灘区にあります。震災から30年が経過し、学生たちにとって30年前の神戸の街の様子が、映像でしか知らない風景となったことを大学側として課題に感じていました。この度の取り組みによって、地元・神戸の過去・現在を学生の目線で考え、神戸の未来を作り上げていく大きなきっかけになることを目指し、川口真規子准教授(※4)が当プログラムへの参加を決定。ゼミ生である沢田佳乃子氏が論文研究の題材として手を上げ、17名のゼミ生の中心となって研究を進めることになりました。川口准教授は、食ビジネス、発酵学、官能評価を専門としており、沢田氏も食品官能評価の手法を学んでいます。

※4 川口真規子准教授
https://gyoseki.acoffice.jp/kswhp/KgApp/k03/resid/S000047


中間発表では沢田氏が「現外の物語を私たちの言葉で伝えたい」と取り組みへの意欲を語り、『現外』の官能評価と阪神・淡路大震災の被害、および震災復興の取り組みに関する調査を行い、6月22日に訪問した『現外』の製造者である沢の鶴株式会社 取締役 製造部部長 西向賞雄氏へのインタビューの様子を発表しました。
インタビューでは、『現外』が熟成し始めてから今に至るまで、造り手にとってどのような存在に変化したかを西向氏に質問しました。「廃棄せずに熟成し続けて良かったと思えるお酒。Clearとの協業により、最良な方法でお客様に届けてくれた」と品質維持の大変さとともに話を聞いた沢田氏は、震災後にやらなければならないことがたくさんあった中、『現外』が神秘的な味わいになるまで維持した沢の鶴の努力に非常に驚いたと発表しました。
また、「今後の味わいの予測は不可能。味わいが変わり、『現外』の素晴らしい価値をお届けできなくなった場合は販売を見送る可能性がある」という西向氏の話を聞き、沢田氏は『現外』について繊細で儚い存在だと感じたと同時に、今後の変化に好奇心を湧かせる魅力的なお酒、と感想を述べていました。
今後の取り組みについて、これらの調査を継続して行うとともに、そこから得た情報を学生自身の心のフィルターを通して人々に伝えるための、リーフレットの作成を提案しました。
共同研究2)神戸学院大学・木暮ゼミプロジェクト「灘の酒リブランディング」に取り組む中で『現外』が持つシンボル的な意味と価値を探ること
神戸学院大学経済学部 木暮衣里准教授(※5)のゼミは、2025年度から産官学連携による「灘の酒リブランディング・プロジェクト」に取り組んでいます。その一環としてSAKE HUNDREDとの共同研究に手を上げました。震災と復興を乗り越えて誕生した30年熟成の『現外』が持つシンボル的な意味と価値を探り、「希望の灯」としてのストーリーを未来に繋ぐために必要となる取り組みや発信の方法について研究しています。

木暮准教授は企業・組織、都市・地域のブランド構築などを専門としており、学生はヒアリング、アンケート等で調査・分析し、課題を抽出した後、アウトプットとしての企画を検討し、実施を目指しています。
※5 木暮衣里准教授
https://kenkyu-web.kobegakuin.ac.jp/Profiles/1/0000061/profile.html
中間発表では、木暮ゼミの3年次生18名を代表して5名が登壇。「灘の酒リブランディング」での取り組みから得た知見、沢の鶴への訪問と『現外』の試飲、プレインタビュー結果等から、『現外』が持つ価値についての発表を行いました。


学生は『現外』の価値について、「沢の鶴が時代を超えて長くつないできた“価値”」と「小さな希望を分かち合える“価値”」のふたつがあると発表しました。神戸学院大学の学生による、阪神・淡路大震災当時についてのプレインタビュー
前者について、搾りたてのフレッシュな日本酒が主流となっている中で敢えて熟成酒の研究に取り組む沢の鶴の姿勢や、『現外』のもととなるお酒を20年以上も見守り続けてきた会社としての決断、SAKE HUNDREDの生駒社長との出会いで世に出ることができたことなどから、地元企業である沢の鶴が創業から300年もの長きにわたり紡いてきた努力がセレンディピティを引き寄せたとと発表。長い時間をかけて真面目に自分たちらしい酒造りを追求してきたことに「時の女神」が微笑んだお酒であると述べました。
後者については、「灘の酒リブランディング」の一環で灘五郷の他3蔵を訪れた学びから得た考えでした。各社が甚大な被害を受けた中でも、それぞれに「小さな希望の灯」を頼りに歩を進めてきた様子を発表。被災した資料館の復興や、倒壊した建物の木材の再活用などを行なっています。このような多くの方々の「小さな希望の灯」を集めることで、より深い“価値”を共創できるブランド・コミュニティーが構築できるのではと、今後の取り組みと合わせて提案しました。
神戸学院大学の学生は研究の中で、『現外』が持つ「希望の灯」のストーリーをどのように感じるかについて、阪神・淡路大震災当時を知る近畿圏在住の方々にプレインタビューを行いました。そこで得た回答を一部ご紹介します。
- 被災した方々の色々な想いが受け継がれているように思います。
- 誰にでも簡単に真似できない唯一無二の存在が、『現外』の価値を生み出していると感じました。
- 生き残った酒母を大切にした分、良質なお酒になっているのではないかと思います。
- 未曾有の大災害で残った酒母は「奇跡的に残った」のではなく「偶然残ったものに関わる、多くの人の想い・意志で残し続け、復活させたもの」と感じました。お酒と町の復活・復興を願いつづけ、希望を持って信じて前だけを向いて生きていくという想いの詰まった特別なお酒があることで、人々は前を向いて生きていけたのではと思います。20年、25年というのはとても長い上に、成功するかも分からない状況の中で、『現外』の存在は「生きていくこと」に直結していたのかもしれません。しかし、商品として販売する以上、消費者からすると「購入する」行為に納得できる価値のある商品・味でなくてはなりませんが、その部分もプロとして答えているところが素晴らしいと感じました。新しいお酒と大震災を語りつづけるお酒の、ふたつの意味を持つ商品だと感じます。
- 私は35年営業一筋で、人と接する心地良さや、自らの行動で社会貢献ができることがモチベーションです。5年、10年、20年と経験を重ねていくと点が線となり、見えないものが見えてくるようになり、他人には分からない経験という付加価値、簡単には真似できない感覚が芽生えます。まさに『現外』のように熟成されなければ得られない『唯一無二』という意味が、私の今までの人生と重なる感じがしました。
共同研究の最終発表会は、2026年1月。両大学合同で神戸にて開催予定
中間発表の後、両大学でワークショップを行い、それぞれの発表に対する感想やフィードバックを共有し合いました。
今後は、神戸松蔭大学と神戸学院大学、それぞれが個別で研究に取り組んできたことを10月に集約し、最終的にひとつの共同研究として、報道関係者および共同研究関係者に向けて、阪神・淡路大震災から31年目となる2026年1月17日前後に最終発表会を開催する予定です。


阪神・淡路大震災を乗り越えた、熟成30年 ヴィンテージ日本酒『現外』
30年前の1995年1月17日に起こった阪神・淡路大震災。7棟あった木造の蔵がすべて倒壊するほどの大きな被害を受けた兵庫県神戸市の酒蔵で、奇跡的に残ったタンクには「酒母」と呼ばれる、醸造途中の液体が入っていました。醸造設備の被災により次の工程に進むことが叶わず、やむなく酒母の段階で搾られ清酒となりますが、当時は香味のバランスが取れておらず、商品化はできませんでした。これが、後に『現外』となるお酒です。


熟成による味わいの変化に一縷の望みを託し、熟成庫で眠りにつくこと数十年。そのお酒には、造り手すら想像しなかった味わいがもたらされました。
長い歳月によってもたらされたアンバー色の風格、複雑でいて芳醇な香り、甘味・酸味・苦味・旨味が一体となった凝縮感を充分に味わいながら、口づけから余韻が消えていくまで、透明感すら覚える上質な体験が続きます。『現外』は阪神・淡路大震災を乗り越え、震災以降の厳しい環境下でも日本酒の可能性を信じた「人間の意志」が宿った奇跡の1本です。

商品名:現外|GENGAI
製造者:沢の鶴(兵庫)
内容量:500ml
価格:¥286,000(税込)
※会員限定販売のため、ご購入にはSAKE HUNDREDの会員にご登録ください。
購入方法:ブランドサイトにて販売
https://jp.sake100.com/products/gengai
世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』SAKE HUNDRED
SAKE HUNDREDは、世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げ、比類なき価値を提供する日本酒ブランドです。最高峰のグローバルブランドとして、味覚だけでなく、お客様の心の充足に貢献し、人と人との豊かな関係を築いていきます。最上の体験によってもたらされる、身体的・精神的・社会的な満足、そのすべてが、SAKE HUNDREDのお届けする価値です。

会員登録で、最新情報や限定商品などをご案内
SAKE HUNDREDでは、最新情報や会員限定のお知らせ、限定商品の販売などを行っております。会員登録は無料ですので、ぜひご登録ください。
SAKE HUNDRED会員登録
https://jp.sake100.com/account/register
会社概要
会社名:株式会社Clear https://clear-inc.net
所在地:東京都渋谷区渋谷2丁目4ー3 JP渋谷4階
設立:2013年2月7日
代表取締役:生駒龍史
資本金:1億円
事業内容:
- 日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」 https://jp.sake100.com
- 日本酒専門WEBメディア「SAKETIMES」 https://jp.sake-times.com